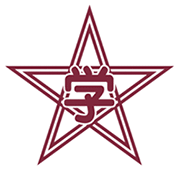入試結果と試験寸評
2026年度 入試結果
2026年度 試験寸評
中学入試結果
| 帰国生入試 | 一次〜三次入試 (帰国生) |
|
|---|---|---|
| 入学試験日 | 12月13日 | |
| 合格発表日 | 12月15日 | |
| 応募者数 | 16名 | --名 |
| 受験者数 | 14名 | --名 |
| 合格者数 | 3名 | --名 |
| 実質倍率 | 4.7倍 | --倍 |
帰国生入試寸評 試験日:12月13日
作文
- 作文の採点では、表記、表現、語彙、文法などに加え、構成力と説得力を重視しました。
本年度のテーマは「国外での生活の中で感じた現地の文化や慣習の素晴らしさ」です。
構成力と説得力
構成力では、「素晴らしさ」の定義と、その経験が中学生活に与える影響を論理的に述べられているかを重視しました。多くの答案で具体的な体験に基づく一貫した構成が見られました。 説得力では、現地の文化・慣習の「素晴らしさ」をどのようにとらえたか、その背後にある価値観まで深く説明されているかを特に重視しました。価値観や歴史に踏み込んだ考察は高く評価されました。一方で、「素晴らしさ」が抽象的で、具体的なエピソードに結びついていない答案や、具体例が適切でない答案も見受けられました。
総評
すべての受験生から異文化理解へのひたむきな姿勢と、広い視野を持つ意欲が伝わってきました。答案のレベルは非常に高く、力作揃いで、採点に苦労するほどでした。
英語力について
- 昨年同様、実用英語技能検定(英検)をはじめとする英語外部試験のスコアを判断基準に用いました。
昨年に引き続き、皆さんが英検のCSEスコアをご提出されましたが、一昨年は、他の外部試験のスコアをお示しくださった受験生もいらっしゃいました。よいスコアであるほど優遇させていただきました。ヨーロッパ言語共通参照枠(CEFR)についても、A1~B2まで、様々でした。英語4技能に注目すると、スコアが高い順に、リーディング > ライティング > リスニング > スピーキング の受験生が多かったです。日本語による作文がうまく書けていた受験生は、昨年同様、ライティングのスコアが高い傾向が見られました。なお、作文との総合判定をする際の得点換算方法は非公表とさせていただきます。